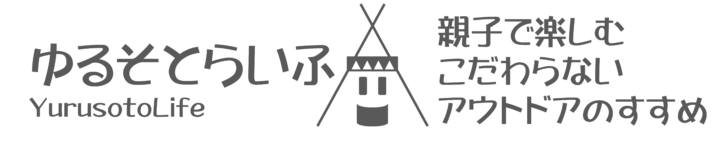こんにちは。
今回は、現在小学校3年生の息子が、熊本のオルタナティブスクールWINGSCHOOL(ウイングスクール)に通い始めてから1年間の話を投稿します。
息子が熊本のオルタナティブスクールに一年間通って変わった3つのこと
首都圏の公立小学校から、私の転勤のタイミングで家族で熊本に引っ越し、オルタナティブスクールに転校して1年。
妻の地元でもあり、私も10年以上住んだ第二の故郷なので、生活には特に不安はなかったのですが、息子の学校にはいろいろと悩みました。
ただ、彼が彼らしく安心して過ごすことができる環境を用意したくて、思い切ってオルタナティブスクールWINGSCHOOL(ウイングスクール)へ一日体験。
息子の希望もあり、その場で入学を決めました。
学校と言えば、公立学校しか知らなかった我々にとって、WINGSCHOOLでの学校生活は驚きと発見の連続でした。
具体的な生活についてはおいおい書きたいと思いますが、今回は、一年間通った中で、息子がこれまでと変わった3つのことについて書きたいと思います。
その3つは以下の通り。
- 爪が伸びるようになった
- 学校から呼び出されることがなくなった
- 「ま、いいか」が口ぐせになった
爪が伸びるようになった

ここ最近、息子の爪が伸びていて、深爪派の私は「これ切らなきゃだめだよー」、と息子に話していました。
それを横で聞いていた妻が、「そういえば、最近爪がよく伸びるようになったね~」とひとこと。
それで改めて気づいたのですが、赤ちゃんの頃は別として、幼稚園から昨年まで、ほとんど息子の爪を切る、ということがありませんでした。
常日頃から爪を噛んだり、むしったりしていたため、切る爪がなかったということです。
ストレスが原因の爪噛みがなくなったから?
爪噛み、爪むしりにはいろいろな理由があると言われていますが、ストレスや不安、緊張などを強く感じた時に、そういった行動に至ることもあるようです。
前の学校から引っ越して、新しい学校に入るということは、息子にとっても非常にストレスがあったと思いますが、それが落ちついてきた、ということかもしれません。
ストレスが無くなった、ということが直接的な要因かはわかりませんが、少なくとも、爪むしりや爪噛みなどが無くなったことは事実です。
単なる成長かもしれません。でも嬉しい変化です。
学校から呼び出されることが無くなった
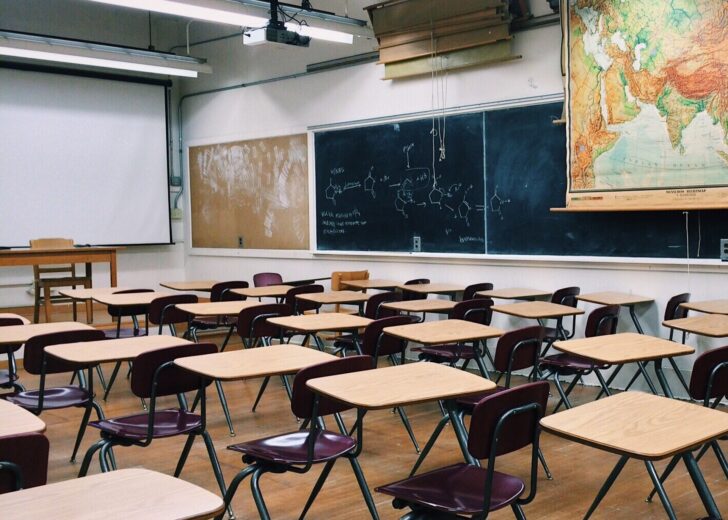
この一年間、息子が原因で学校から呼び出されることはありませんでした。
そもそも、しょっちゅう学校から連絡があって、迎えに行くということが、あまりないことだと思いますが。。。
首都圏の公立小学校に通っていた一年、最初は楽しく通っていたものの、クラスのみんながわちゃわちゃしていた状態から、椅子に座って授業を受けるようになっていく中で、どうしてもその雰囲気に違和感を感じ、だんだんなじむことができなくなっていきました。
それでも、友達と遊ぶのは楽しくて何とか通っていました。
ついには、体調不良になりやすくなり、午後には学校から呼び出しがあり、妻が迎えに行く、ということが多くなりました。
担任の先生からは、できないこと、悪いところを指摘されるばかりで・・・
良いところは何一つ言ってもらえず、我々がへこむことも多い、きつい時期だったと思います。
でもその時、いろいろと子育ての本を夫婦で読み漁ることで、今まで知らなかった発達障害や教育、非認知能力、自己肯定感等に関する知識を得ることができました。
また、療育センターでWISC-Ⅳ検査を行って、客観的に息子の特性を改めて理解できたことも、我々にとっては今思えば大きな収穫でした。
今は・・・
帰りの時間を〇〇時と約束しても、友達と遊ぶのに忙しく、1時間くらいは遅くなるのはしょっちゅう、夕方まで学校で遊んでいる・・・
という先生には非常に迷惑な、学校&先生&友達大好き人間になっています!

「ま、いいか」が口ぐせになった
息子は小さいころから、いろいろなこだわりが強く、我々から見たら「しょーもない」ことにものすごくこだわっていました。
特にリアルへのこだわりは半端なく・・・
家でピザを作ろう!となったら、ピザ屋のメニューを作り、玄関に張り出す、従業員用の立ち入り禁止のドアを作る・・・
手巻き寿司をするなら、プラレールの線路をつなげて、回転ずしの「列車が運んでくれる寿司」を再現するまで食べないなど、細部にまでこだわります。

それを少しでも邪魔しようものなら、ぶちギレて手の付けられない状態に・・・。
何か自分の思い通りにいかないと、所かまわず暴れまわる。。。
子供はそういうものかもしれませんが、ちょっと強烈なタイプかな、と思っていました。
息子のこだわりスイッチが入りそうな瞬間を察知して、そのスイッチが入らないようにすることもありました。
今思えば、それもどうかと思いますが。
そのこだわり自体は今も変わらずで、一度始めると何事も徹底的にやらないと気が済まないのですが、それでも、うまくいかないときには「ま、いいか」と切り替えたり、「落ち着け、俺」と自分で気持ちをコントロールできるようになっています!
これは、WINGSCHOOL(ウイングスクール)で、中学生から小学1年生まで、様々な年齢のメンバーと、分け隔てなく名前やあだ名で呼びあい、ごちゃ混ぜになる中で、自分なりの心の切り替え方が身についてきたのだと思います。
その環境の中で、いろいろなことにチャレンジして、失敗もしているので、切り替える力を学びつつあるんだな、と感慨深いものがあります。

結論:オルタナティブスクールに一年間通って息子は大きく変わったが、親も大きく変わった
息子が熊本のオルタナティブスクールに一年間通って変わった3つのこと、ということで書きましたが、こうやって見ると、息子が変わったことはもちろんですが、我々親も気持ちが大きく変わっていることに気が付きました。
オルタナティブスクールでは、子供たちものびのびと個性豊かに学んでいますが、そこに来る親御さん&先生も一般的な会社員だけではなく、一風変わった(褒めてます!)個性的な(褒めてます!!)方々がいらっしゃる印象です。
非常に刺激的です。
今まで、会社や狭い世界の中では、知ることのできなかった多様な価値観があることを、我々自身が学ぶことで、自分たちの行動も変わるとともに、息子に対する接し方も変わっている気がします。
ぜひ、興味がある方は、オルタナティブスクールの体験をしてみてはいかがでしょうか。我が家はお勧めします。
一日体験や季節によってはサマースクールなどもありますよ。
もちろん、合う合わないは個人差がありますし、家庭内での教育方針は千差万別だと思うので、お子さんに合った学びの場を用意してあげるのが一番であることは言うまでもありません。
とはいえ、オルタナティブスクールって何?
とはいえ、みなさんはオルタナティブスクールという言葉を知っていますか?
少なくとも一年前ちょっと前の私は知りませんでした。
さらに、自分の息子がそこに通うなんて、全く思いもしていませんでした。
息子も自分と同じように、学校は家の近くの公立に入学し、そのまま進学していく、と思い込んでいたからです。
それ以外の選択肢なんて頭からありませんでした。
オルタナティブスクールとは、以下のとおり、今までの学校とは異なる、新しい考え方で運営される学校を指します。
オルタナティブスクール は、現在の公教育=一条校とは異なる、独自の教育理念・方針により運営されている学校の総称です。
総称なので、オルタナティブスクール全体に共通した教育観はありません。
各校それぞれに理念・特色があります。
「不登校をしているから、一条校の代わりに通う」というよりも、その教育観・学校が好きだから、共感するから、心地いいから通う 場所として通うこどもたちがたくさんいます。
オヤトコ発信所より引用
要は、自分に合った学びの場を自分で選んで通うことができる選択肢の一つ、と言うことです。
ウイングスクールでの活動
息子の通っているWINGSCHOOLでは、生徒自らが企画を立てて、いろんなイベントやプロジェクトに取り組みます。
したがって、いわゆる運動会や学芸会などの一般的な学校イベントはほとんどありません。
私も最初は「え、運動会ないの?」とびっくりしました。
小学校の思い出と言えば、良し悪しは別にして運動会が上位に入ると思うからです。
今では、その考えもなくなっていますが。
運動会と言えば、公立小学校一年生の時、5月に運動会があったのですが、とんでもない暑さで生徒はぐったり、家族もぐったり、この中で体育座りさせられているのは、修行でしかない状態でした。
それでもみんな文句を言わず指示に従っている・・・
そんな中、息子は猛暑の中でやる気ゼロ。
早々に保健室へ避難していました。
当時はその姿を見て、「他の子は頑張っているのになんで我慢できないんだ!」と怒り心頭でしたが、今思えば「炎天下で我慢を強いるこんな行事は早々に不参加でOK!」といった考え方もあったな、と感じています。
いまでは、毎日鬼ごっこやケイドロで走り回る等、暑さもなんのその、走ることが大好き人間に変貌を遂げています!
体育の授業や運動会が無くても、放課後の習い事やサッカーが無くても、体はどんどんたくましくなってきています。
本当に楽しい・好きなことは、限界まで取り組むので、トレーニングになっているんだと思います。
写真は、遠足の中でのイベントで、あめ食い競争をやった時の猛ダッシュ!です。

勉強はもちろんありますが、自然の中での体験等で感性が伸びていく、自分でやりたいことを考えて、それを実現するために取り組む。
失敗することもあるけれど、むしろ失敗ばっかりだけど、それによって、レジリエンス(自己回復力)が育まれていると思います。
もちろん、メリットデメリットはあると思いますが、現段階では、我々は選んでよかったと思いますし、その選択に責任をもって向き合えると考えています。
公立小学校に行っていたら、自分で深く考えることなしに、何かと「学校や先生のせい」にしてしまっていた気がします。
ぜひ、学校選びの選択肢として、検討してみてはいかがでしょうか。
その後の生活については、こちらをご覧ください。
それでは、楽しいゆるそとらいふを!